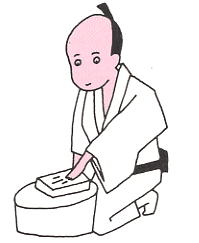 広島針の歴史は、江戸時代にはじまった 広島針の歴史は、江戸時代にはじまった広島の手縫針は、約300年前、藩主の浅野氏が、長崎から木屋治左衛門という針職人をつれてきたことにはじまります。木屋治左衛門は、己斐村(現在の西区己斐)に住み、弟子をとって製針業を創設するとともに、浅野家の下級武士に、内職として針の製法を教えました。 その方法は分業で、先頭は何町で、穴あけは何町でと、専門分野を分けて生産していたようです。生産高はかなり大きく、"みすや針"の名で包装され、船によって、京阪、江戸の針問屋に送られ、日本全国で販売されていましたが、以後200年間は、手工業的に製造されていた状態でした。 機械の導入は明治時代になってから 明治29年、中田和一郎氏が京都からドイツ機械の一部を購入し、機械化への第一歩を踏み出しました。しかし当時は、動力の問題、故障の多発などで、なかなか順調には稼動しなかったようです。その内、他の業者も機械化に関心をよせはじめ、国内での機械調達が困難だと知ると、機械製造業者と相談して、苦心の末、自ら機械の製作に成功していったのです。これが明治末期ごろのこと。 必要に応じて、より精巧な機械を開発していく、広島の針業者のパイオニア精神と優秀な技術力は、このころからの伝統となりました。 戦争が針の輸出を促す 大正3年、第一次世界大戦が起こると、中国では、ドイツやイギリスから針が輸入されなくなり、隣の我が国へ買いつけにくるようになりました。何しろ世界で一番需要の多い中国からの申し出です。地理的に恵まれていた広島は、それまで国内向けの針のみ生産していたのですが、輸出針の生産にのりだし、工場の数も急速に増え、殺到する注文に応えていったのです。当時は中国のみならず、東南アジア、アメリカまで輸出されました。しかしこの好況も、大正9年の世界大恐慌で、鎮静化します。 戦争に影響される針産業 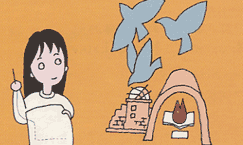 第二次大戦中は、材料の鉄線が配給制となり、強制企業合同のため針製造業者の数は、わずか7社と減少、しかも昭和20年8月6日の原爆で、それらの工場も針もすべてが灰と化してしまったのです。8月15日、戦争が終わり平和が戻ると、針の絶対数不足の状況が生まれました。そこで当時、復興した工場は、針を作れば売れるという活気あふれる状態だったのです。インドの針の思惑買いがはじまり、これまた飛ぶように売れたのですが、当然これは長く続きません。人間のもっとも身近な道具である小さな針は、巨大な戦争という力によって、大きな影響をうけてきました。私たちは、なおさら平和を願わずにはいられません。 第二次大戦中は、材料の鉄線が配給制となり、強制企業合同のため針製造業者の数は、わずか7社と減少、しかも昭和20年8月6日の原爆で、それらの工場も針もすべてが灰と化してしまったのです。8月15日、戦争が終わり平和が戻ると、針の絶対数不足の状況が生まれました。そこで当時、復興した工場は、針を作れば売れるという活気あふれる状態だったのです。インドの針の思惑買いがはじまり、これまた飛ぶように売れたのですが、当然これは長く続きません。人間のもっとも身近な道具である小さな針は、巨大な戦争という力によって、大きな影響をうけてきました。私たちは、なおさら平和を願わずにはいられません。品質の向上を目指して よりよい品質を求めていくことは、私たちの永遠のテーマですが、昭和30年代は"イギリス針に追いつき追いこせ"を合い言葉に、針の頭部に金メッキを施すなどして、努力を重ねた時代です。 |
Copyright (C) 2004 Hiroshima-ken Needle Manufactures Co-operation. All Rights Reserved.